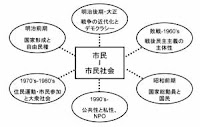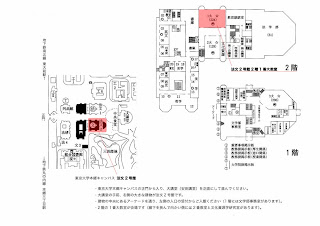■10月5日(金)
〈ゲスト講師〉北川フラム(きたがわ ふらむ)アートディレクター
1946年新潟県高田市(現上越市)生まれ。東京芸術大学卒業。主なプロデュースとして、「アントニオ・ガウディ展」「アパルトヘイト否!国際美術展」等。街づくりの実践では、「ファーレ立川アート計画」「越後妻有アートネックレス整備構想」の総合ディレクター等多数。同プロジェクトによる「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」は2001年の「ふるさとイベント大賞」のグランプリを受賞した。平成18年度芸術選奨文部科学大臣賞(芸術振興部門)受賞。アートフロントギャラリー主宰、地中美術館総合ディレクター、新潟市美術館館長、女子美術大学教授等。
〈ホスト講師〉木下直之(きのした なおゆき)東京大学大学院人文社会系研究科/文化資源学研究専攻
美術を中心に19世紀の物質文化全般を研究対象とする。1954年浜松市生まれ。兵庫県立近代美術館学芸員、東京大学総合研究博物館助教授を経て、2000年より現職。『美術という見世物』(1993年)でサントリー学芸賞。著書に『ハリボテの町』『世の途中から隠されていること』『わたしの城下町』など。
■10月19日(金)
〈ゲスト講師〉中島諒人(なかしま まこと)演出家/鳥の劇場主宰
1990年東京大学法学部卒業。大学在学中より演劇活動を開始、卒業後東京を拠点に劇団を主宰。2003年利賀演出家コンクールで最優秀演出家賞受賞。2004年から1年半、静岡県舞台芸術センターに所属。2006年より鳥取に劇団の拠点を移し、“鳥の劇場”をスタート。二千年以上の歴史を持つ文化装置=演劇の本来の力を通じて、一般社会の中に演劇の居場所を作り、その素晴らしさ・必要性が広く認識されることを目指す。
〈ホスト講師〉小林真理(こばやし まり)東京大学大学院人文社会系研究科/文化資源学研究専攻
文化政策、文化の発展を支える、あるいは阻害する制度を研究している。複数の地方自治体の文化政策の立案・制度設計に関わる。著書『文化権の確立に向けて−文化振興法の国際比較と日本の現実』(2004年)編著『指定管理者制度−文化的公共性を支えるのは誰か−』など。
■11月2日(金)
〈ゲスト講師〉宮城 聰(みやぎ さとし)静岡県舞台芸術センター芸術総監督/演出家
1959年東京生まれ。東京大学文学部中退。大学時代より創造活動を始める。1990年、劇団「ク・ナウカ」を結成。日本の伝統演劇の様式とヨーロッパのテクストを融合させた演出には定評がある。2004年、第12回古代ギリシア劇世界会議に招待され、高い評価を受けた。第3回朝日舞台芸術賞受賞。2005年、第2回アサヒビール芸術賞受賞。2006年、パリにオープンするケ・ブランリー国立博物館ホールのこけら落とし公演に出演。2007年4月より財団法人静岡県舞台芸術センター芸術総監督に就任。
〈ホスト講師〉伊藤裕夫(いとう やすお)富山大学芸術文化学部教授
1972年東京大学文学部卒後、(株)電通入社。1988年より電通総研へ出向、アーツマネジメント、文化政策、および民間非営利活動を主な研究テーマとして取り組む。2000年、静岡文化芸術大学教授に就任、2006年4月より現職。著書に、『NPOとは何か』(共著・日本経済新聞社)『文化経済学』(共著・有斐閣)『アーツマネジメント概論』(共著・水曜社)他。
■11月16日(金)
〈ゲスト講師〉並河恵美子(なみかわ えみこ)特定非営利活動法人芸術資源開発機構(ARDA)・代表
35年続いたルナミ画廊(銀座)を1998年閉廊。その間、若手作家の育成、海外交流に力を入れ日豪交流の基礎を築く。1999年、国際セミナー「みんなで作る地域活動とアート・センター」、ドキュメント2000プロジェクト助成で「高齢者ホームへ出張・展覧会とワークショップ」を実施。2000年「立川国際芸術祭」芸術監督。2002年、杉並在住の美術関係者とNPO芸術資源開発機構を設立。2005年から「アート・デリバリー:介護する人される人のための出張芸術講座」を実施中。
〈ホスト講師〉村田 真(むらた まこと)美術ジャーナリスト
1954年東京生まれ、東京造形大学卒業。ぴあ編集部を経てフリーランスの美術ジャーナリストに。新聞・雑誌に執筆するほか、ウェブマガジン『artscape』に展評を連載。著書に『美術家になるには』、訳書に『ビジュアル美術館12絵との対話』などがある。慶応義塾大学・学習院女子大学非常勤講師、横浜BankARTスクール校長。
■11月30日(金)
〈ゲスト講師〉加藤種男(かとう たねお)アサヒビール芸術文化財団事務局長
アサヒビール大山崎山荘美術館の運営、アサヒ・アートフェスティバルのプロデュースなど、1990年以来、同社のメセナ活動を推進。企業メセナ協議会研究部会の部会長として、わが国の企業メセナをリード。また、「創造都市」の旗振り役として、自治体へ文化政策を提言し、現在は横浜市芸術文化財団専務理事を兼務。NPO活動の推進にも取り組み、アートNPOリンク理事をはじめ、日本NPO学会理事などを務める。大仏次郎記念館館長、埼玉県芸術文化財団理事ほか。著書:『新編 アーツ・マネジメント』(共著)など。
〈ホスト講師〉ニコル・クーリジ・ルーマニエール 東京大学大学院人文社会系研究科/文化資源学研究専攻
1999年、英セインズベリー日本藝術研究所設立と同時に所長就任。現在、東京大学大学院で客員教授を勤める。米ハーバード大学博士課程修了(美術史)。日本の装飾美術と装飾の概念、東アジアにおける近代陶磁器と貿易ネットワーク、および蒐集の歴史についての研究を行う。著書に『400 Years of Japanese Porcelain』(大英出版より出版予定)『Crafting Beauty in Modern Japan』(大英出版)など。
■12月7日(金)
〈特別講師〉鷲田清一(わしだ きよかず)大阪大学理事・副学長
1949年生まれ。京都大学文学部卒業。関西大学教授、大阪大学教授を経て、現職。専門は哲学・倫理学。現象学の視点から、身体、他者、顔、規範、所有、モード、老い、国家などを論じてきた。近年は哲学的思考をケアや教育など社会のさまざまな現場につなげる「臨床哲学」のプロジェクトに取り組んでいる。主著に『モードの迷宮』(サントリー学芸賞)『「聴く」ことの力』(桑原武夫学芸賞)『メルロ=ポンティ』『老いの空白』『「待つ」ということ』など。
■12月21日(金)
〈ゲスト講師〉大谷 燠(おおたに いく)NPO法人DANCE BOX Executive Director
大阪生まれ。1991年から2001年までTORII HALLプロデューサー。1996年、「DANCE BOX」を立上げ、ジャンルを超えたコンテンポラリーダンスの公演・ワークショップを年間約30本企画制作する。2002年DANCE BOXをNPO法人化。大阪・新世界フェスティバルゲート内に「Art Theater dB」を開設し、アーティストの育成と地域社会とアートの新しい環境づくりに力を注ぐ。近畿大学国際人文科学研究所講師。神戸大学国際文化学課非常勤講師。関西経済社会研究所文化アドバイザー。
〈ホスト講師〉曽田修司(そた しゅうじ)跡見学園女子大学教授
東宝株式会社演劇部を経て、1990年代以降、国際舞台芸術交流センター等で舞台芸術に関する国際交流、アーツ・マネジメントを専門領域として活動。2002年、跡見学園女子大学教授。2004年、特定非営利活動法人STスポット横浜理事長。2004年度より、国際交流基金評価に関する有識者委員会委員。
■平成20年1月11日(金)
〈ゲスト講師〉平田オリザ(ひらた おりざ)劇作家/演出家/大阪大学コミュニケーションデザイン・センター教授
1962年東京生まれ。国際基督教大学教養学部卒業後、在学中に結成した劇団「青年団」を率いて、自ら支配人をつとめるこまばアゴラ劇場を拠点に活動、「現代口語演劇理論」を確立する。1995年『東京ノート』で第39回岸田國士戯曲賞を受賞したのをはじめ多数の賞を授与される。2003年、日韓国民交流記念事業『その河をこえて、五月』(新国立劇場制作)で、第2回朝日舞台芸術賞グランプリを受賞。代表作の『東京ノート』は現在9カ国語に翻訳され、海外での評価も高い。2002年度より中学2年生の国語教科書にワークショップの方法論が導入される。三省堂小学校国語教科書編集委員も務める。
〈ホスト講師〉古井戸秀夫(ふるいど ひでお)東京大学大学院人文社会系研究科/次世代人文学開発センター・文化資源学研究専攻
1951年東京生まれ。早稲田大学文学部演劇科卒業。同教授を経て、現在、東京大学教授。専攻は歌舞伎研究。著書に『歌舞伎—問いかけの文学』(ぺりかん社)『新版舞踊手帖』(新書館)『歌舞伎入門』(岩波ジュニア新書)、編著に『歌舞伎登場人物事典』(白水社)などがある。